dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します
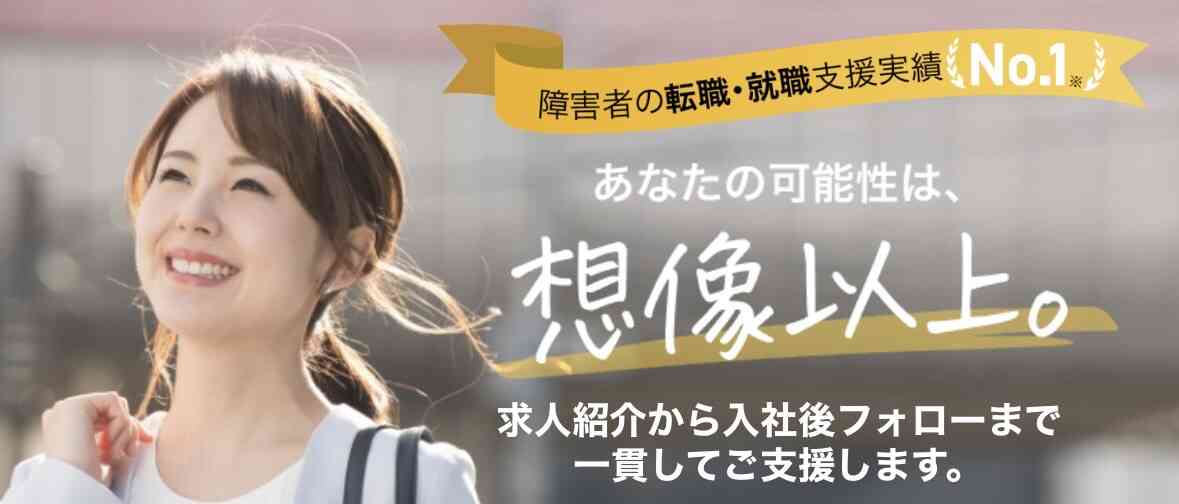
dodaチャレンジは、障害者のための転職支援サービスとして多くの実績がありますが、利用者の中には「断られた」という声も聞かれます。せっかく登録したのにサポートが受けられないと、不安になってしまう方もいるでしょう。
しかし、断られるにはいくつかの理由があり、改善の余地がある場合も少なくありません。この記事では、dodaチャレンジで断られた理由や、断られやすい人の特徴について解説します。どのように対策をすれば再チャレンジができるのかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
転職エージェントに登録しても、紹介できる求人がないという理由で断られるケースがあります。これは、希望条件が厳しすぎたり、職種や勤務地が限られている場合に多いです。
エージェント側は求職者と企業双方にとってマッチする求人を紹介する必要があるため、条件が合致しないと紹介が難しくなります。特に専門性が高い職種や、地方での求人は限られていることが多く、紹介が難航する場合があります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
希望条件が細かく厳しすぎると、該当する求人の数が大幅に減少します。在宅勤務のみ、フルフレックス、年収500万円以上などの条件は、企業側も限定的な募集を行っているため、エージェントが紹介できる案件が見つかりにくくなります。条件の見直しも検討しましょう。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
特定の職種や業種だけを希望していると、求人数は当然限られます。特にクリエイティブ系やアート系など専門性が高い分野は、求人が少なく競争率も高くなるため、紹介が難しい場合があります。幅広い選択肢を持つことも重要です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
勤務地を特定のエリアに限定していると、その地域の求人状況によっては紹介が困難になります。地方は都市部に比べて求人数が少ないため、柔軟な勤務地選びが求められます。働き方や通勤範囲を広げると、可能性が広がることがあります。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
障がい者手帳を持っていない場合は、サポートを断られることがあります。多くの就労支援サービスでは、「障がい者雇用枠」の求人紹介を行っていますが、原則として障がい者手帳の所持が応募条件となっています。
そのため、手帳を持っていない場合は、対象外と判断されることがあるので注意が必要です。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
障がい者雇用枠での求人に応募する場合、原則として障がい者手帳の所持が必要とされています。企業は手帳の有無を基準に法定雇用率の達成状況を判断するため、手帳の提示が求められることが一般的です。手
帳を持っていない場合は、障がい者雇用枠での応募は難しく、一般枠での応募を検討する必要があります。ただし、一部の企業や自治体によっては、医師の診断書などで代替できる場合もありますので、事前に確認しましょう。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
長期間のブランクがある場合や、職務経験がほとんどない場合は、就職活動に不安を感じる方も多いでしょう。特に、生活状況が不安定で継続的な就労が難しいと判断されるケースでは、いきなり一般就労を目指すよりも、まずは就労移行支援を利用することが勧められます。
就労移行支援では、働くためのスキルを身につけたり、職場環境に慣れたりするためのサポートが提供され、段階的に無理のない就職を目指すことが可能になります。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
体調や精神面が不安定な場合、すぐに一般企業での就労は難しいと判断されることがあります。その際は、まず「就労移行支援」を案内されるケースが一般的です。就労移行支援は、安定した就労を目指すための訓練やサポートを受けられる福祉サービスで、体調管理やスキル習得、職場実習などを通じて、自分に合った働き方を見つけるための準備期間になります。まずは無理なくステップアップを目指すことが大切です。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
面談での印象や準備不足が、スカウト後に断られる原因になることがあります。企業はスカウトを送る段階で興味を持ってくれていますが、実際の面談でマナーが悪かったり、企業研究が不十分だと評価が下がってしまうことも。
特に「なぜこの企業なのか」「自分がどのように貢献できるか」を説明できないと、企業側は熱意を感じにくくなります。事前準備をしっかり行い、面談には前向きな姿勢で臨むことが大切です。
障がい内容や配慮事項が説明できない
企業の採用担当者は、障がいの内容や必要な配慮について具体的な説明を求めることがあります。しかし、自分自身で整理できていないと、うまく伝えられず、業務への影響や配慮の方法が不明確になってしまいます。
自身の障がいの特性や職場で必要なサポートについて、あらかじめ整理し、簡潔に説明できるよう準備しておくことが重要です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
やりたい仕事が定まっていなかったり、働く目的やキャリアプランが曖昧な場合、企業に熱意や意欲が伝わりにくくなります。「何のために働きたいのか」「自分はどんな役割で貢献したいのか」を明確にし、面接や書類でアピールできるようにしておくことが大切です。
職務経歴がうまく伝わらない
過去の経験やスキルをうまく説明できないと、あなたの強みや能力が企業に伝わりません。職務経歴は、担当業務や成果を具体的に整理し、誰が聞いてもわかりやすいように説明することが必要です。職務ごとに取り組んだことや達成した結果を数字や具体例で説明すると効果的です。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応の転職サービスですが、地方エリアではどうしても求人数が限られてしまう傾向があります。特に、都市部に比べると障害者雇用枠の求人が少ないため、希望条件に合致する案件が見つかりにくくなるのです。
また、リモートワーク希望の場合も、企業側の受け入れ態勢が整っていないことがあり、選択肢が狭まってしまうことがあります。条件を少し広げるとチャンスが広がる場合もあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
dodaチャレンジは全国対応していますが、地方在住者にとっては求人が限られていることがあります。特に北海道、東北、四国、九州などの地域では、障がい者雇用枠を設けている企業が少なく、求人の選択肢が狭まることがあります。
大都市圏に比べて企業数や求人の種類が少ないため、地方在住者は求人の選択肢が限られていることが理由で断られることがあります。しかし、dodaチャレンジでは、地方に合った求人を厳選して紹介するので、希望に近い求人を見つけられる可能性はあります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
dodaチャレンジは全国対応していますが、完全在宅勤務を希望する求職者に対しては、求人がかなり限定されることがあります。特に障がい者雇用においては、在宅勤務の求人が少なく、企業側のニーズにも制限があります。
完全リモート勤務のみを希望する場合、その選択肢は限られてしまい、希望に合った求人が見つからないことが原因で断られることがあります。dodaチャレンジでは、リモートワーク可能な求人も紹介していますが、希望する条件を満たす企業が少ない場合もあります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、登録時の情報に不備や虚偽があると、信頼性に欠けると判断され紹介がストップする場合があります。正確で誠実な情報入力が重要です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
dodaチャレンジに登録する際、障がい者手帳を取得していないにもかかわらず、手帳を取得済みと誤って記載した場合、虚偽の情報として扱われることがあります。このような不備があると、求人に応募しても採用に至らない可能性が高くなります。
正確な情報を提供することが、転職活動を成功させるためには非常に重要です。手帳をまだ取得していない場合は、その旨を正確に記載することが求められます。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
dodaチャレンジへの登録に際して、自分の健康状態や生活状況を無視して無理に登録を行った場合、適切な求人が見つからない、または断られることがあります。
例えば、現時点で働くことが難しい状況にありながらも、求人を応募してしまうと、後から無理が生じ、活動がスムーズに進まなくなります。自身の状況を正確に把握し、登録前に必要な準備が整っていることを確認することが重要です。
職歴や経歴に偽りがある場合
dodaチャレンジに登録する際、職歴や経歴に虚偽の情報を記載することは大きなリスクを伴います。企業は求職者の過去の実績や経験を重視して選考を行うため、虚偽が発覚した場合、その信頼性が損なわれ、内定を得ることが難しくなります。
誠実な情報提供が求められるため、過去の職歴やスキルを正直に記載することが、転職活動を成功させるために欠かせません。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジで断られたと感じるケースの中には、実際にはdodaチャレンジ側ではなく、企業側の選考で不採用となっている場合も少なくありません。特に、企業の障害者雇用に対する体制や受け入れ環境が整っていないことが理由で、スキルや経験とは無関係に選考から外れるケースもあります。そのため、「dodaチャレンジで断られた」と感じても、悲観しすぎずに他の求人への応募を続けることが大切です。
不採用は企業の選考基準によるもの
dodaチャレンジで求人に応募した結果、不採用となることがありますが、これは企業側の選考基準によるものであり、dodaチャレンジ自体が断ったわけではありません。企業は求職者のスキルや経験、職場のニーズに基づいて採用を決定します。そのため、dodaチャレンジから紹介された求人でも、企業が他の候補者を選ぶことがあります。
不採用になった場合、フィードバックを求めて次のステップに活かすことが大切です。dodaチャレンジはあくまで求職者と企業を繋ぐ役割を果たしているため、選考結果は企業側の判断によるものです。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
dodaチャレンジに登録した求職者の一人は、障がい者手帳を持っていたものの、これまでの職歴が軽作業の派遣のみで、PCスキルもタイピング程度しかなく、特別な資格もなかったため、紹介できる求人がないと言われてしまいました。
求職者のスキルや経験が求人の要件に合わなかった場合、企業から求められるスキルを満たしていないため、求人の選択肢が限られてしまうことがあります。この場合、スキルアップや資格取得が必要になる場合もあります。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
別の体験談では、継続して就労できる状態が確認できなかったため、dodaチャレンジから「まずは就労移行支援を受けて、安定した就労訓練を受けることをおすすめします」と言われました。
障がい者雇用の場では、求職者が健康面で安定していない場合、企業が求める安定した就業能力を示すことが難しくなるため、就労移行支援や職業訓練を受けることが重要です。これにより、安定した状態で転職活動を再開することが可能になります。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
精神疾患で長期療養し、10年以上のブランクがあった求職者は、dodaチャレンジに相談した際に、「ブランクが長く、直近の就労経験がないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう」と提案されました。
長期間働いていない場合、企業側が求職者の健康面や働く能力を懸念することがあり、まずは体調を整え、職業訓練でスキルや経験を再構築することが重要だとされました。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
四国の田舎町に住む求職者は、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。しかし、dodaチャレンジからは「ご希望に沿う求人はご紹介できません」と言われました。地域や職種に特化した求人は限られており、希望する職種が少ない場合、マッチする求人を見つけるのは難しいことがあります。
特に在宅勤務や専門的な職種については、求人が少ないため、地域や希望条件に合った求人を見つけるための工夫が必要です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。
アルバイトや短期派遣での経験しかない求職者は、dodaチャレンジに登録した際、「現時点では正社員求人の紹介は難しいです」と言われました。
正社員の求人には、安定した職歴や経験が求められることが多く、特に長期間のアルバイトや短期派遣経験しかない場合、正社員に転職するためのスキルや実績が不足していると見なされることがあります。そのため、正社員求人に応募する前にスキルアップや職歴の積み重ねが重要になります。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
子育て中の求職者は、完全在宅で週3勤務、時短勤務、事務職、年収300万円以上という条件を出しましたが、dodaチャレンジからは「ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しい」と言われました。
特に、時短勤務や在宅勤務などの希望条件をすべて満たす求人は限られており、柔軟な働き方を希望する場合は、条件に合った求人を見つけるのが難しいことがあります。希望に沿う求人がない場合は、条件を調整することや、別の職種や業種を検討することが必要です。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
精神障がい(うつ病)の診断を受けている求職者は、dodaチャレンジに登録しようとした際、「障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい」と言われました。障がい者雇用枠での求人を提供するには、通常、障がい者手帳が必要とされる場合が多いです。
手帳がない場合、障がい者雇用枠の求人紹介が難しくなることがあるため、手帳取得を前提に再度相談する必要があります。手帳がない状態でも一般の求人を紹介してもらえる場合もあるので、他の選択肢についても確認することが重要です。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
軽作業を長年していた求職者が、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいとdodaチャレンジに相談したところ、「未経験からエンジニア職はご紹介が難しい」と言われ、求人の紹介がありませんでした。
ITエンジニア職は専門的なスキルが求められるため、未経験者がその職種に転職するのは難しいことがあります。この場合、関連するスキルを身につけるための職業訓練や、まずはサポート業務などでの経験を積むことが、転職活動を成功させるためには重要です。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
身体障がいがあり、通勤が困難な状況で週5フルタイムの勤務が難しいと感じていた求職者は、dodaチャレンジに短時間の在宅勤務を希望して相談したところ、「現在ご紹介できる求人がありません」と断られました。
身体障がいを持っている場合、特にフルタイムや通勤が難しい場合には、条件に合った求人が限られてしまいます。求人の数自体が少ないため、条件を変更するか、より適したサポートを受けるための支援が必要です。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
前職が中堅企業の一般職で、今回は障がい者雇用枠で管理職や年収600万以上の求人を希望した求職者は、dodaチャレンジで「ご紹介可能な求人は現在ありません」と言われました。
障がい者雇用枠では、管理職や高年収の求人が非常に限られており、求職者の希望条件に合う求人を見つけることが難しい場合があります。このような場合、希望条件を柔軟に調整するか、他の職種や業界での転職を検討することが必要です。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジは障害者の就職・転職支援を専門に行っているサービスですが、希望通りにいかず「紹介できる求人がない」と断られてしまうこともあります。特に初めての転職活動やブランクがある方にとっては、不安が大きくなる瞬間かもしれません。ここでは、dodaチャレンジで断られたときの原因や、前向きに再スタートするための対処法を紹介します。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
dodaチャレンジで断られる理由の一つに、「職歴が浅い」「軽作業や短期バイトのみの経験しかない」「PCスキルが不十分」といったスキル面の課題があります。このような場合は、今すぐに正社員就職を目指すよりも、まずはスキルアップや職務経験を積むステップを踏むことが大切です。
職業訓練や在宅ワーク、短期派遣などを活用して経験を増やすことで、再チャレンジしたときに紹介される求人の幅が広がる可能性があります。焦らず、段階を踏んで準備することがポイントです。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
dodaチャレンジでスキル不足や職歴不足を理由に断られた場合、ハローワークの職業訓練を活用することが効果的です。ハローワークでは、無料または低額でPCスキルやビジネスマナーを学べるプログラムが提供されています。
特にWordやExcel、データ入力など、基本的なPCスキルを身につけることで、求職者の市場価値を高め、求人紹介の幅を広げることができます。スキルアップを図ることで、再度dodaチャレンジを利用する際の有利な条件が整います。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援を活用することも有効です。就労移行支援は、障がい者向けに提供されているサービスで、実践的なビジネススキルやビジネスマナーを学びながら、職場適応力を養うことができます。
また、メンタルサポートも受けられるため、精神的なサポートが必要な場合にも非常に有益です。就労移行支援を通じて、求職者の自信を高め、企業側に対して安定した雇用ができる能力をアピールできるようになります。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
スキルや職歴に不安がある場合、資格取得は非常に有効な対策です。特に、Microsoft Office Specialist(MOS)や日商簿記3級などの資格は、求人紹介の幅を広げる大きなポイントになります。
これらの資格は、一般的なビジネススキルを証明するものであり、企業側に対してあなたのスキルを客観的に示すことができます。資格を取得することで、自信がつき、転職活動をさらに有利に進めることができます。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養機関があるなど)の対処法について
dodaチャレンジでブランクが理由で断られた場合は、焦らずまず「就労移行支援」などのステップを活用するのがおすすめです。働くことへの不安が強い、長期の療養があった場合には、就労に向けた準備段階として支援機関を利用することで、生活リズムの安定やスキルの習得ができ、次の転職活動につながります。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
ブランクが長く、働くことに不安がある場合、就労移行支援を利用することが有効です。就労移行支援は、障がい者向けに提供されるサービスで、生活リズムを整えながら実践的なビジネススキルを学ぶことができます。
毎日通所することで、安定した就労実績を作り、徐々に自信を取り戻すことができます。また、就労移行支援は精神的なサポートも提供しており、働くことへの不安を解消するための重要なステップとなります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
長期間働いていなかった場合、短時間のバイトや在宅ワークを活用して実績を作るのも一つの方法です。週1〜2回の短時間勤務から始めることで、徐々に働くことに慣れ、安定した勤務ができることを証明できます。
これにより、再度転職を考えた際に、「継続勤務できる」ことを企業にアピールでき、履歴書に自信を持たせることができます。短時間勤務は、無理なく社会復帰するための第一歩となります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
長期的なブランクがある場合、企業実習やトライアル雇用に参加することで実績を積むことができます。実習では、実際の業務を体験しながら、企業との相性を確認することができるため、雇用前に自分に合った職場かどうかを判断できます。
また、実習での成果を基に、再登録時にアピール材料として活用でき、転職活動において有利に働きます。実習を通じて、再就職への準備を進めることができます。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
dodaチャレンジで地方在住のため求人紹介がなかった場合は、まず「在宅勤務・フルリモート可能な求人」に希望条件を絞り直すのが有効です。通勤圏内に案件が少なくても、オンライン勤務可能な企業ならチャンスが広がります。また、他の転職エージェントや障害者向け求人サイトを併用するのも一つの手段です。複数のサービスを活用しながら、自分に合った働き方を探していきましょう。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
地方在住で通勤可能な範囲に求人が少ない場合、在宅勤務OKの求人を探すことが効果的です。dodaチャレンジ以外にも、atGP在宅ワークやサーナ、ミラトレなどの障がい者専門の転職エージェントを併用することで、リモートワークや在宅勤務を希望する求職者に最適な求人を見つけやすくなります。
これらのサービスは、特に障がい者のニーズに対応した求人を多く取り扱っており、地方在住者でも柔軟に働ける環境を提供しています。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
地方に住んでいる場合、地域の求人に限りがあるため、クラウドソーシングを活用して実績を作るのも一つの方法です。ランサーズやクラウドワークスなどのプラットフォームを使い、ライティングやデータ入力などの仕事を始めることで、リモートワークの実績を積むことができます。
これにより、在宅ワークを希望する求職者が、スキルを証明し、他の求人に応募する際の強力なアピール材料となります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地域密着型の求人情報を得るために、地元の障がい者就労支援センターやハローワークに相談することも重要です。これらの機関は、地域に特化した求人情報を提供しており、通勤可能な距離で求人を見つける手助けをしてくれます。
また、地元の企業に特化したサポートが受けられるため、地方在住者にとって非常に役立つ情報源となります。地域のニーズに合った求人を提供してもらえる場合もあります。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
希望条件が多すぎると、dodaチャレンジでも紹介できる求人が見つからないことがあります。完全在宅や週3勤務、希望年収などをすべて満たす求人は非常に限られるため、条件を一部緩和するのが現実的です。優先順位をつけて、どの条件なら譲れるかを整理し、キャリアアドバイザーに再相談してみるのがおすすめです。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
希望条件が厳しすぎて求人紹介が断られた場合、まずは希望条件に優先順位をつけることが重要です。「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を明確に分けることで、アドバイザーに対して柔軟な対応ができるようになります。
例えば、年収や勤務時間は譲れない部分とし、勤務地や勤務日数などは調整可能な条件として見直すことで、マッチングの幅が広がり、求人紹介を受けるチャンスが増えます。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
求人紹介が難しい場合、譲歩できる条件を再提示することも一つの方法です。勤務時間や出社頻度、勤務地など、最初に提示した条件を見直して柔軟に対応できる点をアドバイザーに伝えましょう。
例えば、完全在宅勤務にこだわっていた場合、週に数回の出社も許容範囲に含めることで、より多くの求人を紹介してもらえる可能性が高まります。条件を見直すことで、適切な求人を見つけやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
希望条件が厳しくて求人紹介を受けられない場合、段階的にキャリアアップを目指す戦略を立てることが有効です。最初は希望条件を少し緩めてスタートし、仕事に慣れながらスキルを磨くことが重要です。
例えば、年収や勤務条件が理想的でなくても、経験を積むことでキャリアアップでき、後に理想的な働き方が可能となります。段階的にキャリアを積んでいくことで、長期的な目標に向かって確実に進むことができます。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジでは、障がい者手帳の有無や支援区分によって紹介可能な求人が限られるため、手帳未取得や精神・発達障がいで区分が合わない場合には断られることがあります。その際は、自治体の障がい者就労支援センターやハローワーク、他のエージェントを併用することで、より自分に合った支援を受ける道が広がります。焦らず他の選択肢を検討しましょう。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
障がい者手帳が未取得の場合、まずは主治医や自治体に相談して手帳申請を行うことが重要です。精神障がいや発達障がいの場合でも、条件が整えば手帳を取得することができます。
特に、症状が安定している場合や支援が必要な状況が明確な場合、手帳の取得が認められる可能性があります。申請の際に必要な書類や手続きについて、医師としっかり相談し、スムーズに申請を進めることが手帳取得への第一歩となります。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳が未取得の場合、dodaチャレンジ以外の方法を検討するのも良い対策です。就労移行支援やハローワークでは、障がい者手帳なしでも応募できる求人を探すことができます。
一般枠での就職活動を行うか、就労移行支援を経てからdodaチャレンジに戻ることで、求職活動を継続できます。手帳なしでもサポートを受けられる求人があるため、まずはこれらの機関を通じて求人情報を集めることが有効です。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
精神障がいや発達障がいが原因で手帳取得が難航している場合、まずは体調管理や治療を優先することが大切です。手帳を取得するためには、安定した健康状態が求められることがあります。医師と相談し、治療やリハビリに専念しながら体調を整えることで、再度手帳申請を行う際に有利になります。
体調が安定し、手帳が取得できるようになったタイミングで再登録し、転職活動を進めることができるでしょう。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジ以外にも、障がい者向けの転職支援サービスは多数存在します。例えば、atGPやミラトレなど、異なるエージェントを利用することで、求人の幅を広げることができます。
また、障がい者雇用に特化した別のサポートを提供する機関を利用することで、自分に合った職場を見つけやすくなります。dodaチャレンジ以外のサービスも併用して、より多くの選択肢を探ることが有効です。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジは、障害者雇用専門の転職支援サービスとして知られていますが、精神障害や発達障害の方の中には「紹介を断られた」と感じるケースもあるようです。実際には、就労経験や希望条件、障害の特性に応じて紹介の難易度が変わるため、一概に不利とは言い切れません。まずは自分の特性に合ったサポート内容を把握することが大切です。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を所持している方は、比較的安定した雇用先を紹介されやすい傾向にあります。特に視覚や聴覚、肢体不自由などの障害は企業側も配慮しやすく、就業環境の整備も進んでいます。dodaチャレンジでも企業とのマッチングがスムーズに行われやすいです。就職活動の際は、職務経験や通勤可能範囲など具体的な情報をしっかり伝えることが成功のポイントになります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
障がい者手帳の等級が低い場合、企業側の配慮が少なくても仕事がしやすいと見なされることが多く、就職がしやすい傾向があります。軽度の障がい者は、業務の幅が広がり、特別な配慮が少なくても働けることが多いため、求人の選択肢も増えます。企業も採用に対して柔軟に対応しやすいため、就職活動を進めやすいです。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
具体的な支援が必要であれば、企業側も配慮しやすく、環境を整えることが比較的簡単です。見た目で障がいが明確なため、職場内でどのような支援が必要かがわかりやすく、企業側の対応もスムーズです。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がいがある場合、企業側は合理的配慮を明確にしやすいです。たとえば、バリアフリー化や業務制限を設けることで、障がい者が働きやすい環境を整えることが可能です。このように具体的な配慮が求められ、企業側もどのように対応すればよいかが明確になるため、採用に対して安心感を持ちやすくなります。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
上肢や下肢の障がいがある場合、通勤や作業に制約があるため、求人が限られることがあります。例えば、通勤が困難であったり、特定の作業が難しい場合、求人自体が少なくなります。しかし、在宅勤務やリモートワークが可能な求人もあるため、そのような職種を選ぶことで就職活動が円滑に進むことがあります。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
コミュニケーションに問題がない場合、身体障がいや精神障がいを持っていても、一般職種への採用が多いです。特に、対人スキルや業務遂行能力に支障がない場合、企業側は特別な配慮が必要ないと判断し、一般職種での採用を検討するケースが多くなります。障がい者であっても、仕事のパフォーマンスに支障がなければ広範囲の職種に応募できます。
PC業務・事務職は特に求人が多い
PC業務や事務職は、障がい者向けの求人が特に多い分野です。これらの職種では、物理的な障がいに関係なく、スキルを活かすことができるため、幅広い求人があります。PCを使った業務や事務作業では、障がい者でも快適に働ける環境が整えられやすく、在宅勤務などの柔軟な働き方が可能な求人も多いため、特にこの分野での就職は比較的しやすいです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持っている人の就職は、配慮が必要な点が多く、企業とのマッチングが難しい場合もあります。dodaチャレンジでは支援実績が豊富ですが、症状や職場環境の相性によっては紹介が難しいこともあります。希望に合った職場を見つけるためには、障害特性の自己理解と継続的なサポートの活用が重要です。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障害者保健福祉手帳を持つ求職者にとって、就職活動では症状の安定性や職場での継続勤務が重視されます。企業は、症状が安定しており、長期的に安定して働けるかどうかを確認したいと考えています。従って、就職を決定する際には、自己管理の方法や職場適応の可能性が大きなポイントとなります。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは見えにくいため、企業は「採用後の対応」に不安を感じやすいのが現実です。障がい者が職場にどのような影響を与えるかが明確でないため、企業は配慮やサポートが必要かどうかを判断するのが難しいと感じます。これにより、精神障がい者雇用に対する不安がある場合もあります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
採用面接時には、配慮事項の伝え方が非常に大切です。自身の障がいに関する情報を適切に伝えることで、企業側がどのようにサポートすればよいか理解しやすくなり、採用への道が開けます。配慮事項を明確かつ前向きに伝えることが、面接を通過するための重要なステップとなります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職では、障害者雇用枠を活用して安定した職場に就くケースが多いです。ただし、業務内容やサポート体制の整備が必要とされるため、企業によって受け入れに差があります。就職支援機関の利用も効果的です。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳を持つ人の就職事情では、A判定(重度)とB判定(中軽度)の区分によって就労の選択肢が大きく異なります。A判定の人は一般就労が難しく、主に福祉的就労支援(就労継続支援B型)が中心となります。B判定の人は、より幅広い職種に挑戦でき、一般就労を視野に入れることが可能です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の場合、精神的または身体的な支援が必要なため、一般就労が難しいことが多いです。そのため、福祉的就労である就労継続支援B型などが主な選択肢となります。就労継続支援B型では、職場での支援を受けながら働くことができ、適切な環境で仕事に取り組むことが可能です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の場合、知的障がいが比較的軽度であるため、一般就労の選択肢が広がります。一般就労でも、必要な支援を受けながら働くことができるため、企業側の理解を得やすいです。B判定の人は、専門の支援機関や就労移行支援を通じて、一般企業で働く準備を進めることができるため、職種の選択肢が増えます。
障害の種類と就職難易度について
障がい者の就職活動では、障がいの種類や程度によって就職難易度が大きく異なります。身体障がいや精神障がい、知的障がいなど、さまざまな障がいの種類があり、それぞれの障がいに対する企業の理解や配慮の程度も異なります。例えば、身体障がいの場合、見た目で障がいが分かるため企業が適切な配慮をしやすいですが、精神障がいや発達障がいの場合は、障がいが見えにくいため、企業側が採用後のサポートに不安を感じることがあります。
障がい者雇用の求人は増えているものの、障がいの種類や職種によっては、求職者が希望する条件の仕事を見つけることが難しい場合もあります。この記事では、障がいの種類ごとの就職難易度について詳しく解説します。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害者雇用枠とは、企業が障害のある方を対象に設ける特別な採用枠で、勤務時間や仕事内容、配慮事項などが個別に調整されやすいのが特徴です。一方、一般雇用枠は健常者と同じ条件で選考や勤務が行われ、特別な配慮は原則として期待できません。自身の体調や特性に合わせて、どちらの雇用形態が合っているかを見極めることが大切です。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、企業が障害者雇用促進法に基づいて設定した雇用枠で、企業が法律に従って一定割合の障がい者を雇用することが義務づけられています。この枠は、障がい者の就労機会を確保するための重要な制度です。障害者雇用枠に該当する求人には、障がい者向けの配慮がなされており、応募する際に障がいをオープンにして働くことが一般的です。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用促進法に基づき、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月から引き上げ)を障がい者として雇用する義務があります。この法的義務により、企業は一定の障がい者雇用枠を設け、障がい者を雇用することが求められます。これにより、障がい者の就労機会が確保されるとともに、企業も社会的責任を果たすことになります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、応募者は自分の障がいをオープンにし、必要な配慮事項を企業に明確に伝えた上で雇用されます。企業は、障がいに対して必要な配慮(例えば、作業環境の整備や勤務時間の調整)を提供し、安定した就労を支援します。これにより、障がい者は自分の特性に合った働き方を実現しやすくなります。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障害の有無に関係なく、すべての応募者が同じ条件で競う採用枠です。この枠では、障がい者も含めて、すべての求職者が同じ採用プロセスを通じて選考されます。障がい者が応募する場合でも、他の応募者と同じ条件で評価されるため、自己アピールやスキルを重視した選考が行われます。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠で働く場合、障がい者は障害を開示するかどうかを自分で決めることができます。開示する場合はオープン就労、開示しない場合はクローズ就労となります。オープン就労では、障がいに対する配慮が受けられる場合もありますが、クローズ就労では配慮を受けることなく働くことが基本です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、障がい者に対する特別な配慮や措置は基本的にありません。企業側は、障がいを開示しない限り、障がい者に対して特別な配慮をする義務はなく、通常の従業員と同様に扱われることが一般的です。ただし、障がいを開示した場合には、必要に応じて配慮がされることがあります。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者雇用率は、年代別に異なる傾向が見られます。特に若年層と高齢層では、採用の難しさに違いがあり、それぞれの年代に応じた課題や需要があります。若年層の障がい者は、就職活動の際に経験が不足していることが多く、企業側はその点を懸念材料にすることがありますが、一方で、学歴やポテンシャルを重視する企業も増えてきています。
高齢層では、長期間の職歴や経験を持っている一方で、年齢が高いことで再就職の難しさが生じることもあります。年代による障害者雇用の傾向を理解することは、求職者自身の戦略を立てる上で重要です。この記事では、年代別の障害者雇用率の特徴と、その違いについて解説します。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
若年層(20〜30代)の障がい者雇用率は高く、企業も若手の育成を重視する傾向があります。特に求人数が多く、未経験でも採用されやすい場合があります。企業側は、若年層を採用することで、長期的に企業に貢献してもらえる可能性が高いと見なすため、柔軟な働き方やサポート体制を整えた求人が増えているのが特徴です。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以降の障がい者は、求人数が減少し、採用の難易度が高くなる傾向があります。特に、「スキルや経験」が求められる場面が多く、転職活動においてはその点が強調されます。企業は即戦力を求めるため、スキルや実務経験がない場合、求人に応募することが難しくなることがあります。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の障がい者の場合、フルタイム勤務の求人が限られ、短時間勤務や特定業務に限定されることが多いです。企業は、年齢を重ねた従業員には特別な配慮を求める場合があり、仕事の負担を減らすために、勤務時間を短縮したり、特定の業務に集中させたりする傾向があります。これにより、求職者の希望条件に合う求人を見つけるのが難しくなることがあります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジなどの就活エージェントでは、明確な年齢制限は設けられていないことが多いですが、実際には20代~40代前半までの転職希望者を中心にサービスが提供される傾向があります。年齢や経験によっては、紹介可能な求人が限られる場合もあるため、事前に相談するのがおすすめです。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジをはじめとする就活エージェントには明確な年齢制限は設けられていませんが、実際のところ、50代前半までがメインターゲット層となっています。
年齢が上がるにつれて、企業が求めるスキルや経験、長期的な勤務の見込みなどが重視されるため、求人の幅が狭くなり、年齢が高いほど難易度が上がることがあります。ただし、年齢に関係なく、自分に合った職場を見つけるためのサポートは提供されています。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
dodaチャレンジなどの就活エージェントだけでなく、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)を併用することも非常に有効です。これらの機関では、地域に特化した求人情報を提供しており、幅広い求人選択肢から自分に合った職場を見つけやすくなります。
また、専門的な支援を受けることができるため、就職活動をサポートしてくれる重要な情報源となります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスとして高く評価されています。口コミでは、キャリアアドバイザーが親身にサポートしてくれる点や、求人の質が良いとの声がありますが、一部では担当者の対応に差があるとの意見もあります。全体的には、手厚いサポートと、個別のニーズに応じた求人提案に満足する利用者が多いです。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで求人に断られた場合、まずはフィードバックを求めて、断られた理由を明確にしましょう。その理由を元に、自分のスキルや経験を改善する方法をアドバイザーと相談することが大切です。また、別の求人を探すために、アドバイザーに再度相談することで、別のチャンスが広がります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談後に連絡がない場合、いくつかの理由が考えられます。アドバイザーが求人の調整やフィードバックを整理しているため、連絡に時間がかかることがあります。また、求人が見つからなかった場合や、進行中の求人選考が長引いていることもあります。連絡が遅れている場合は、直接アドバイザーに確認して進捗状況を聞くことが重要です。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、まずは障がいの特性や希望する職場環境について詳しくヒアリングされます。その後、これまでの職歴やスキル、キャリアの目標に基づいて、適切な求人を提案されます。また、面接での注意点や、職場で必要な配慮についても相談しながら進めます。アドバイザーからのアドバイスを受けて、具体的な転職活動を進める流れになります。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスで、求職者一人ひとりの障がいに配慮した求人提案を行います。専門のキャリアアドバイザーがサポートし、面接対策や書類添削、アフターフォローまで手厚く提供します。求人には、障がい者雇用に理解のある企業を厳選して紹介しており、求職者が安心して就職活動を進められる環境が整っています。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジのサービスは、障がい者手帳を持っていない場合でも利用可能です。障がいに関連する特性がある求職者には、手帳がなくてもサポートを提供しています。手帳を持っていない場合でも、自分の障がい特性をアドバイザーに伝えることで、適切な求人を提案してもらえます。手帳なしでも、障がい者雇用枠での求人を探せる場合があります。
関連ページ:dodaチャレンジは手帳なしで利用できる?障害者手帳は必須!申請中でも利用できます
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、ほとんどの障がいに対応した転職支援を提供していますが、極端に高い医療支援や特殊な職場環境が必要な障がいがある場合、求人の選択肢が限られることがあります。ただし、ほとんどの障がいに対応可能で、個別に配慮された求人を提案しているため、具体的な障がいについてアドバイザーに相談することで、適切なサポートを受けることができます。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジの退会は、担当キャリアアドバイザーに退会希望を伝えることで手続きが開始されます。その後、アドバイザーと確認しながら、個人情報削除を行い、最終的に退会となります。退会理由についてフィードバックが求められることがありますが、再度利用したい場合には、再登録が可能です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン面談または対面で受けることができます。オンライン面談は自宅から参加でき、対面面談はdodaチャレンジの拠点で実施されます。どちらも、求職者のニーズに合わせて柔軟に対応されます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限はありませんが、一般的に求人の対象としては20代〜50代前半が中心となります。年齢が高くなると、求人の選択肢が限られることがあるため、年齢に応じたサポートが提供されます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは離職中の方にも利用可能です。離職中でも、就職活動のサポートや求人紹介、面接対策などを提供しています。無職の状態でも、専門的な支援を受けながら次のステップを進めることができます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは学生にも利用可能です。特に、卒業後の就職活動やインターンシップを探す学生には、障がいに配慮した職場を提案してくれるサービスがあります。学生の場合、就職活動をスムーズに進めるためのサポートを受けることができます。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスとして多くの求職者に利用されていますが、「断られない」とは言い切れません。サービス提供者としての役割は、求職者と企業をつなぐことですが、求職者の障がいの種類やスキル、経験に合った求人がなければ、紹介が難しい場合もあります。
dodaチャレンジでは障がい者雇用に特化した求人を提供し、手厚いサポートを行っているため、多くの求職者が自分に合った職場を見つけやすくなっています。また、他の障がい者就職サービス(例えば、atGPやミラトレ)との比較を行うことで、サービスの特長や強みを理解し、より自分に適した支援を受けることが可能です。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
関連ページ:LITALICOワークスの口コミ・評判|利用者が語るリアルな声と就職支援の実力
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
dodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスとして多くの求職者に利用されていますが、求人紹介を受けられなかったり、断られたりすることもあります。断られた理由には、いくつかの要因が考えられます。例えば、求職者のスキルや経験が求人の要件に合わなかった場合や、障がいの種類や程度に応じた求人が見つからない場合です。特に、求職者が希望する職種や勤務地が限定的であったり、障がいに対する企業側の配慮が必要な場合、求人の選択肢が少なくなることがあります。
また、精神障がいや発達障がいなどの見えにくい障がいの場合、企業が「採用後の対応」に不安を感じることがあり、求人紹介が難しくなることがあります。こうした場合、自己管理の方法や過去の職務経験、必要な配慮事項について、面接時に明確に伝えることが重要です。
dodaチャレンジで断られた場合の対処法としては、まず断られた理由をアドバイザーに確認し、それを元に改善策を考えることです。例えば、スキル不足が原因であれば、ハローワークの職業訓練を受けてスキルを向上させたり、就労移行支援を活用して働く準備を整えることが効果的です。また、希望条件に柔軟性を持たせることで、求人の選択肢を広げることができます。